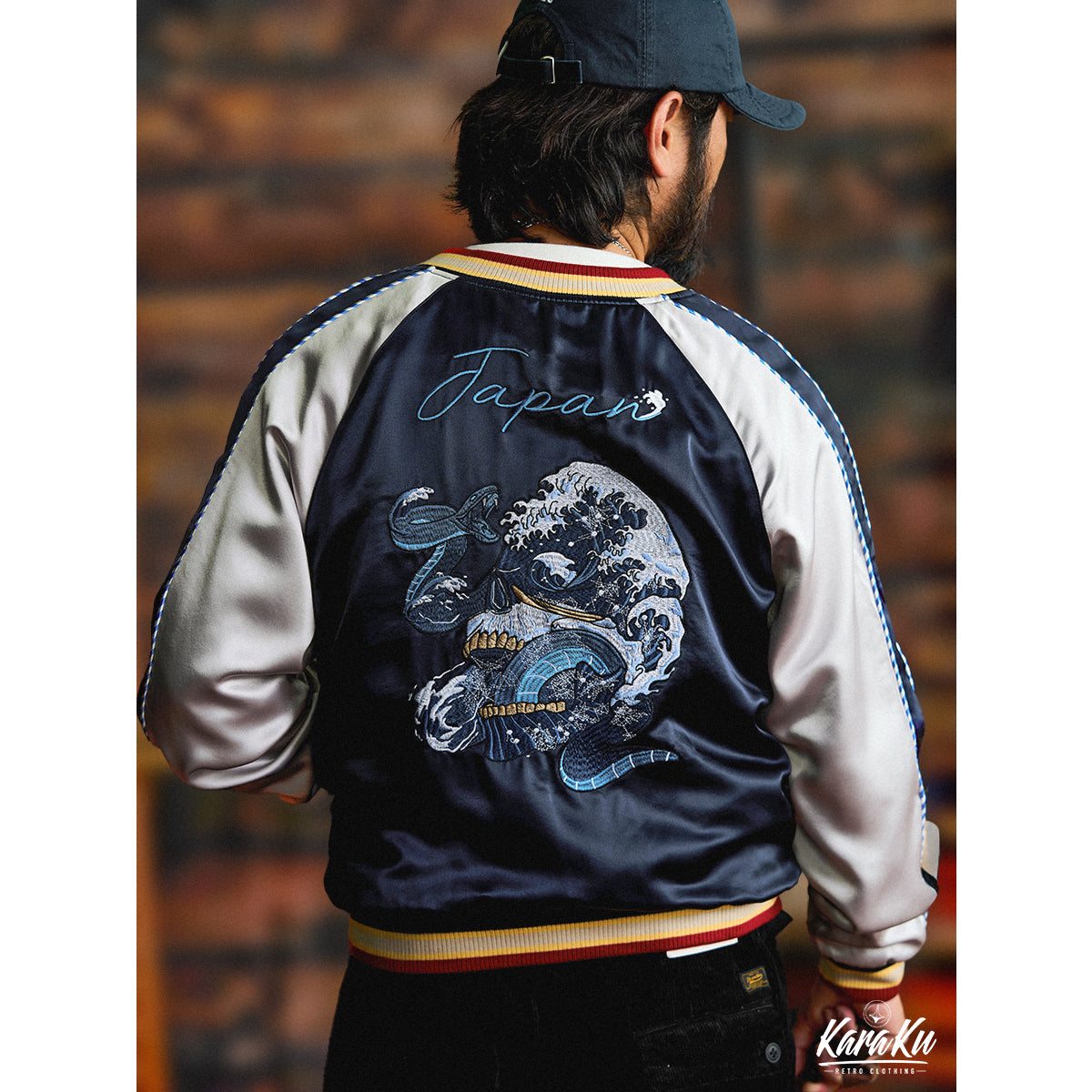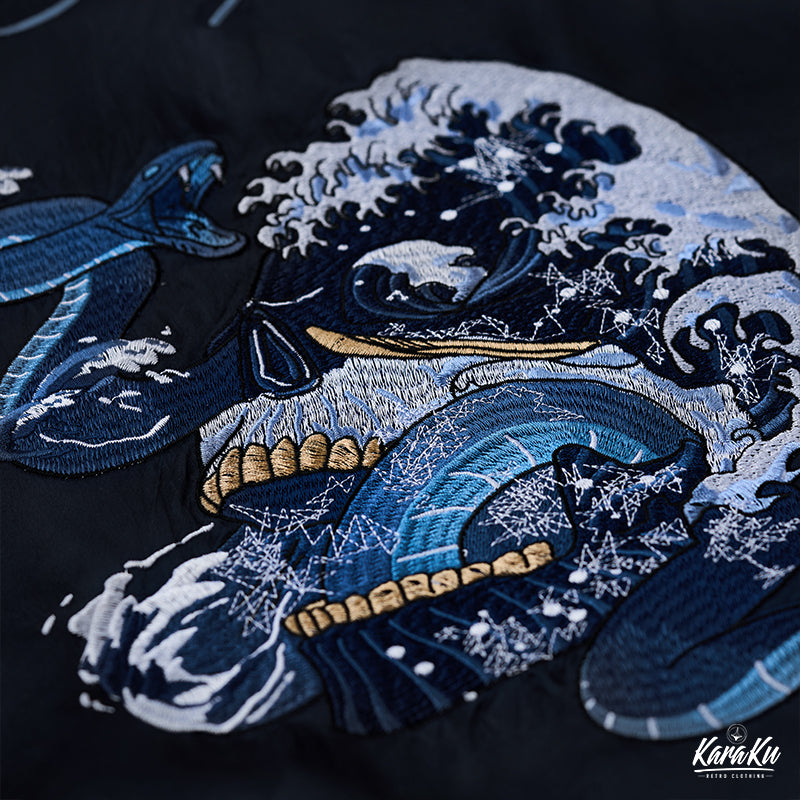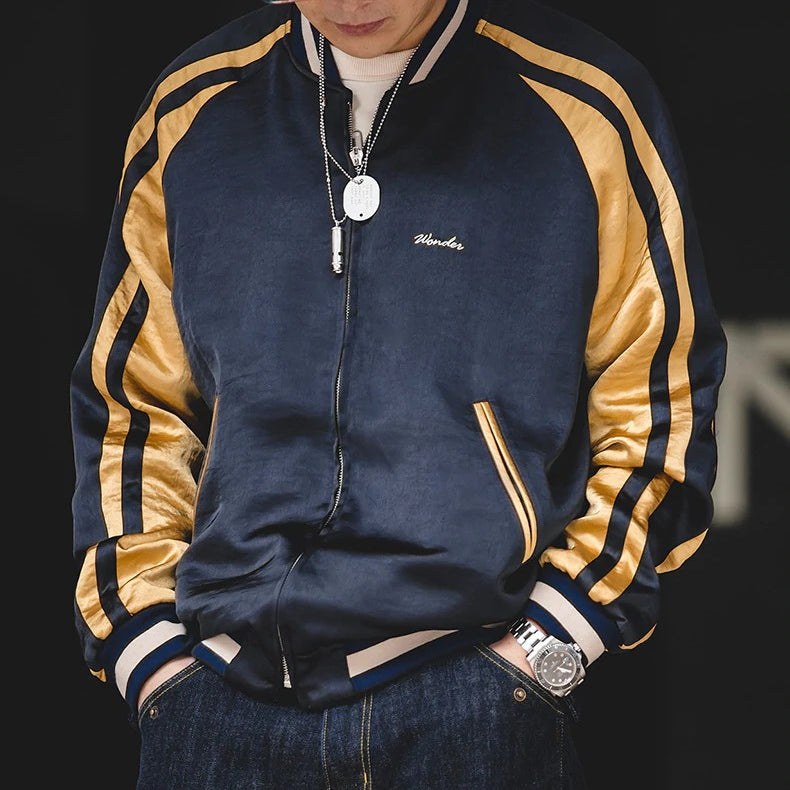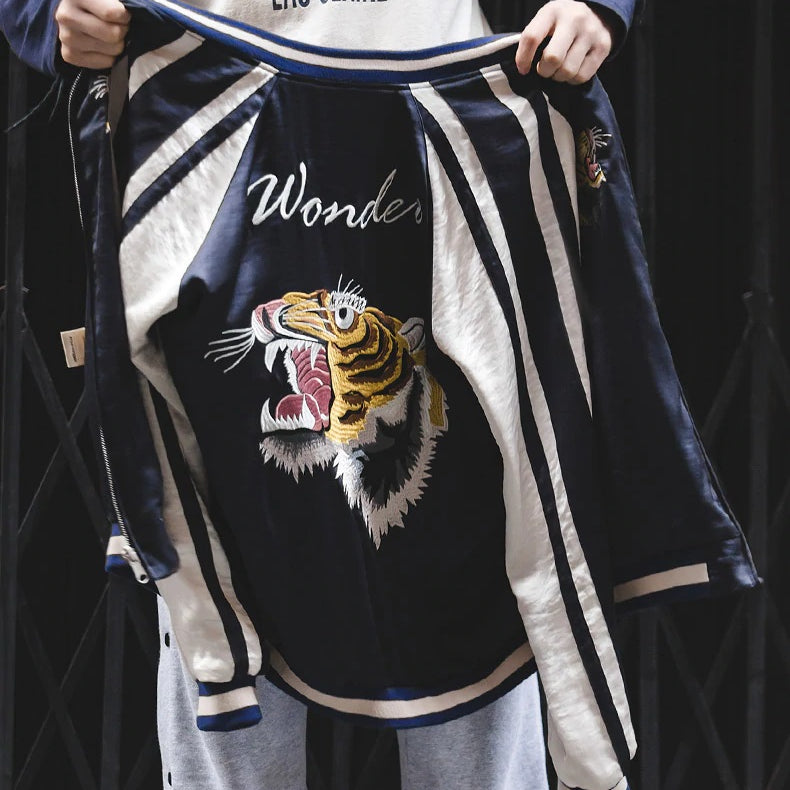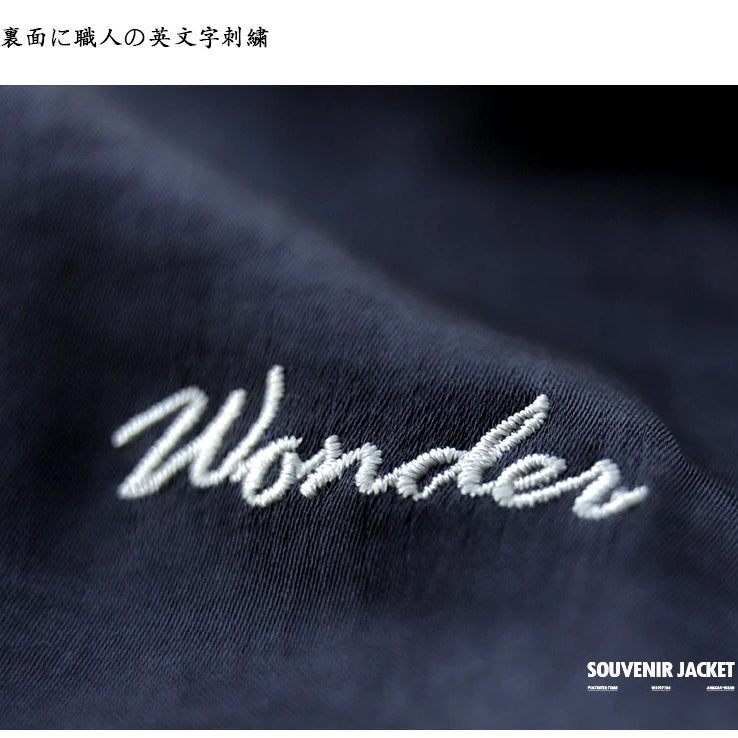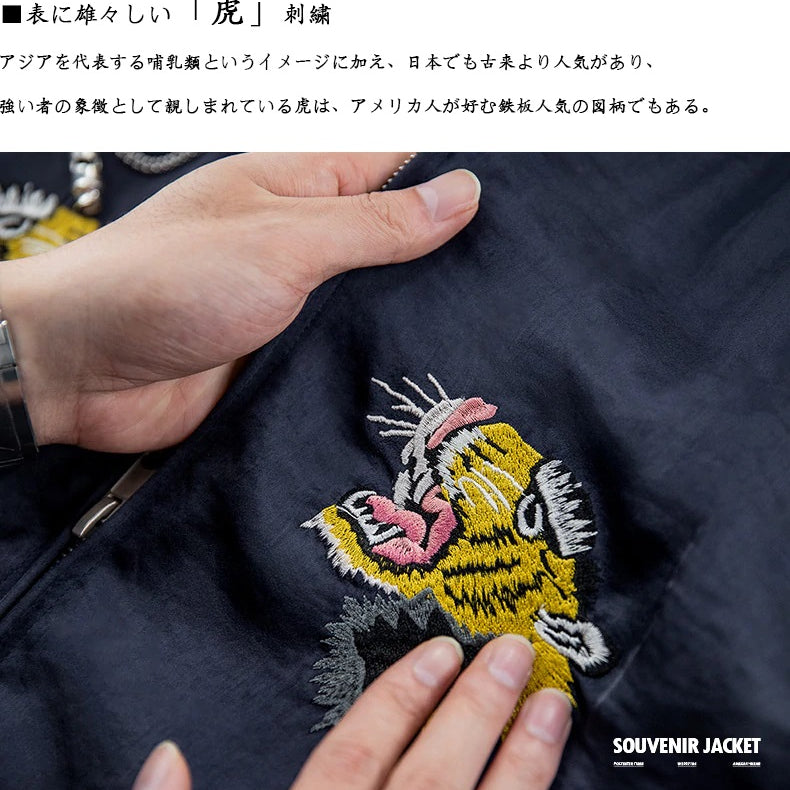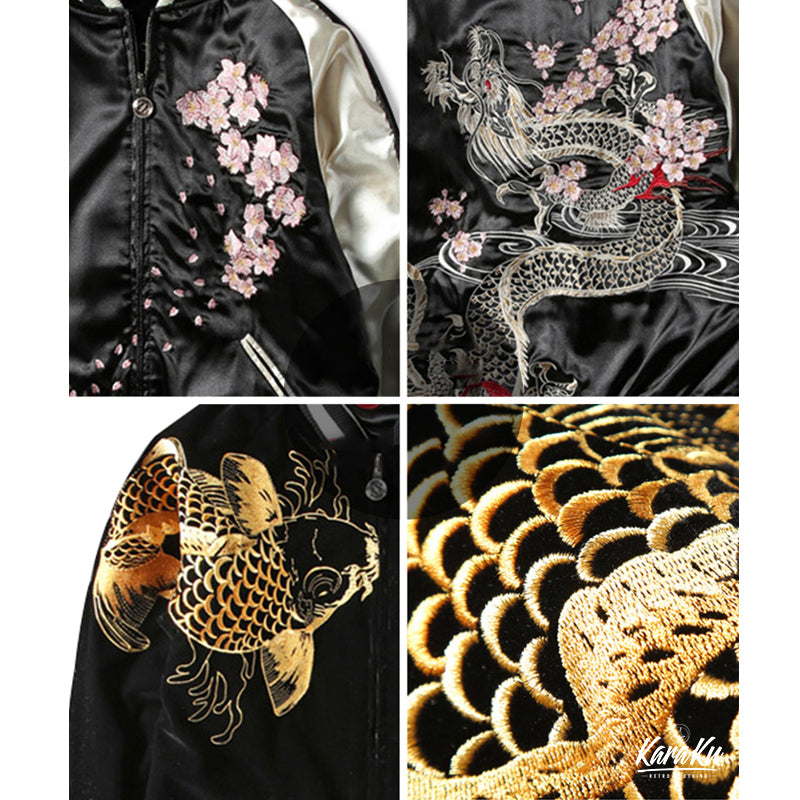スマホ片手にイヤホンをつけた武士が、
真剣な表情で何かをスクロールしている。
「江戸Tik風?今、江戸がバズってる?」
──そんな言葉に思わず笑ってしまった人もいるかもしれません。
けれど、このイラストに描かれているのは、
単なるギャグではありません。
今から約200年前の江戸時代にも、**今でいう“サブカルチャー”**が、
しっかりと息づいていたのです。
例えば、壁一面に描かれた“むだ書”(=落書き)。
それは、当時の人々──ときには武士さえもが描いた、笑いと遊び心の集大成でした。
「粋(いき)」とは何か?
そして、なぜ現代のファッションにそれを取り入れるのか?
今回のブログでは、江戸のユーモア、国芳の美学、そしてKARAKUが提案する“着られるアート”について、4つの視点から紐解いていきます。
目次
01|江户のサブカル?
02|誰が誰なのか?
03|粋”の本質に迫る
04|国芳の遊び心 × 現代のファッション
※リンクをクリックすると、項目の説明に遷移します~
※画像タップで商品ページに飛べます!
01|江戸にもサブカルがあった!

グラフィティといえば現代のストリートアートを想像しますが、
実は江戸時代の日本にも、壁に描かれた落書き=むだ書(無駄書)が存在していました。
この“江戸版グラフィティ”とも言えるのが、
歌川国芳による浮世絵「荷宝蔵壁のむだ書」。
そこには、武士たちが退屈しのぎに描いたであろう顔芸、
滑稽な表情、意味不明な文字がずらり。
まさに、江戸の壁が語っていたのです。
「グラフィティは西洋だけの文化じゃない。
日本にも“壁の声(ウォールボイス)”があった。」
現代のBanksyのように、辺境の表現がカルチャーの主流になっていく。
そんな文化の移ろいも、ここから見えてきます。
02|誰が誰なのか?

例えば、この女性。「花ぞの」と書いてあります。
歌川豊国『五節句之内文月 斎藤太郎左衛門永井室花園」

「花ぞの (花園)」とは役の名前で、四代目尾上梅幸の当たり役なんだそうです。
梅幸は上品な美人を演じるのがピカイチだったとか。

ところで、この猫は一体?

頭中をかぶって、楽しそうに踊っている??
この猫の正体は......

歌川国芳『見立東海道五捨三次岡部猫石の由来』
後ろの大きな大きな化け猫、ではなく。
左下の子。
尻尾が二股に分かれているのが猫の妖怪「猫又」の証なんとか。
! !左側の子は、嬉しくて尻尾ぶんぶん振ってるのかと思ってました!!
03|粋”の本質に迫る
“粋(いき)”とは、ただオシャレであることではありません。
ちょっとハズした遊び心、人をクスッとさせるユーモア、余白を楽しむ知性……
そんな“型破りなのに品がある”感覚こそが、江戸の粋。
この浮世絵に描かれたむだ書たちは、まさにその象徴です。
「ふざけているのに、美しい。」——それが粋。
この精神を現代のファッションに取り込むことが、KARAKUの提案するスタイルです。
04|国芳の遊び心 × 現代のファッション

歌川国芳といえば、反骨精神とユーモアを兼ね備えた浮世絵師。そんな彼の精神を、KARAKUは“着るアート”として現代に再構築しました。
この「落書き風プリントアロハ」は、ただの和風シャツではありません。
それは「ルールに従うだけじゃつまらない」「自分らしさを表現したい」——
そんな想いを込めた一枚。
「こんなふざけた絵が、世界に誇る浮世絵。」
そして、あなたがそれを纏うとき。
江戸の遊び心が、また一つ、現代に息づくのです。
商品詳細ページ:
歌川国芳「荷宝蔵壁のむだ書」落書き風プリントオープンカラーシャツ
--------------------------------------------------
【✨KARAKU 5周年記念セール・最大60%オフ!✨】
--------------------------------------------------
【✨KARAKU×石黒亜矢子・コラボレーション企画✨】
--------------------------------------------------
【✨2025 SPRING SUMMER✨】
--------------------------------------------------
【✨MAX 55% OFF 在庫処分セール✨】
--------------------------------------------------
【✨2025 SS KARAKU ✨】
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
※karakubuy公式SNSも是非フォローお願いしますね!